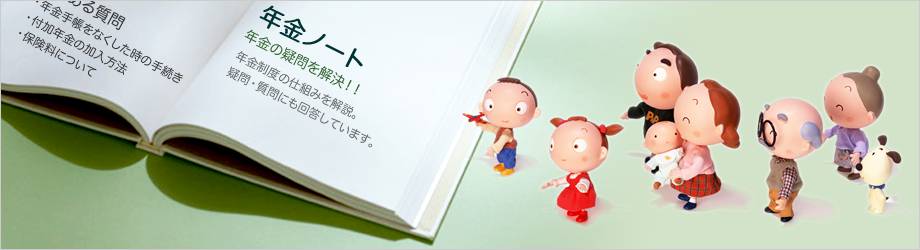付加年金の申し込み方法・手続きを解説

老齢基礎年金額に上乗せできる付加年金について、わかりやすく説明いたします。
手続き簡単、お手頃価格で年金を増やせるので、加入したいと思った方は、ぜひ参考にして手続きしてください。
- 付加年金とは?
- 付加年金への加入条件
- 付加年金の申し込み・手続き
- 付加年金の加入期間いつからいつまで?
- 付加保険料納付の権利を喪失する場合
- 付加年金の額
- 付加年金の注意事項
- 付加年金の支給停止と失権
- 付加年金は損?得?
付加年金とは?
「老後に受け取ることができる年金の額を増やしたい」と、思っている人は多いのではないでしょうか?
そんな方にお勧めなのが、付加年金制度への加入です。
月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金受給時に、「200円 X 付加保険料納付済期間の月数」で算出した額が加算されます。
納付額が400円で支給額が200円なので、一見、損しているような感じですが、納付した額を2年で回収し、3年目以降はまるまる得するお得な年金制度です。
例えば、付加保険料を10年間(120月)納付したとすると、2年受給すれば、納めた総額の4万8000円に達するので、3年目から1年ごとに2万4000円得します。
【納めた総額】 400円 X 120月 = 48,000円
【1年間に支給される額】 200円 X 120月 = 24,000円
この様に、納付額がいくらであっても、2年間受給すれば納付額に達します。
付加年金への加入条件
付加年金に加入できるのは、次の人たちです。
付加保険料を納めることができるのは、第1号被保険者(国民年金のみの加入者)です。ですから、第2号被保険者(サラリーマン・OL・公務員)とその被扶養者である第3号被保険者は加入できません。また、第1号被保険者であっても、保険料免除者、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できません。
付加保険料の納付が義務付けられています。
任意加入被保険者は付加保険料を納付することができますが、特例任意加入被保険者は加入できません。
付加年金の申し込み・手続き
第1号被保険者は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月から付加保険料を納付することができます。
実際の付加年金の手続きは、お住まいの市区町村役場で簡単に済ますことができるので安心してください。
年金手帳、そして、本人でない場合は認印が必要です。
上記の必要な物を持参して市区町村役場の年金課窓口に行き、付加年金の手続きをしたい旨を伝えると、『国民年金付加保険料納付申出書』を渡されるので、必要事項を書き込むだけです。
記入項目は少ないので、2、3分もあれば完了するでしょう。
何日か経過すると、年金事務所から『国民年金付加保険料納付申出受理通知書』が送られてきます。
その後、納付書が送られていくるので、納期限までに付加保険料を納めてください。
付加年金の加入期間いつからいつまで?
付加保険料は保険料納付済期間のみに納付できます。
したがって、最高で40年間(480月)です。
【納めた総額】 400円 X 480月 = 192,000円
【1年間に支給される額】 200円 X 480月 = 96,000円
国民年金保険料滞納期間、保険料免除期間は当然として、追納した場合も付加保険料を納付できないので注意してください。
付加保険料納付の権利を喪失する場合
付加保険料を納付している人は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、付加保険料の納付を止めることができます。
実際には、申出日の属する月の前月以後の各月から付加保険料を納付しない者となります。
また、「付加保険料を納期限までに納めない場合」や「国民年金基金の加入者となった場合」も、付加保険料を納付する権利を喪失します。
付加年金の額
付加年金の額は、「200円 X 付加保険料納付済期間」です。
老齢基礎年金額等が物価スライドによって変わっても、付加年金額は200円固定で変わりません。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ・繰下げ支給した場合、同じ率によって減額・増額されます。
この減額・増額された額は、一生変わりません。
付加年金の注意事項
付加年金には、次の特徴があります。
昭和61年4月1日前は、第3号被保険者の国民年金への加入が任意であったため、付加保険料を納めることができました。したがって、その期間に基づく付加年金は、老齢基礎年金と合わせて支給されます。
国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した場合、その加入員であった期間は、付加保険料納付済期間とみなされます。
2014年4月以降の期間に限り、2年前までの付加保険料を納付できるようになりました。
付加年金の支給停止と失権
付加年金は老齢基礎年金に併せて支給されます。
したがって、老齢基礎年金が全額支給停止されているときは、付加年金も支給停止されます。
そして、受給権者が死亡した場合は、付加年金も失権します。
付加年金は損?得?
ここまで付加年金について説明してきて、2年で元が取れるので、第1号被保険者か任意加入被保険者なら付加年金に加入した方が得であることは十分理解できたと思います。
しかし、次の場合、付加年金に加入して損します。
- 老齢基礎年金受給後2年経つより前に亡くなる
- 将来、生活保護を受けるようになる
1は、もらった付加年金額が、払った付加保険料額に達しないので、その差額分損です。
2は、お住まいの地域や家族構成によって生活保護の金額は異なりますが、単身世帯の場合、「老齢基礎年金と付加年金の合計金額」よりも「生活保護費」の高くなるか、ほぼ同額なので、損です。
つまり、生活保護費が最低支給額となるため、「老齢基礎年金 + 付加年金 < 生活保護費」の場合、付加年金に加入していた人も加入していなかった人も、支給される生活保護費は同額となります。
将来のことはわかりませんが、「非正規雇用増加」「結婚率低下」「高齢者増加」「生活保護の受給世帯増加」という状況を考えれば、付加年金に加入しても2に該当する人が多くなるのは間違いないでしょう。
この2つが、付加年金に加入した際のリスクです。