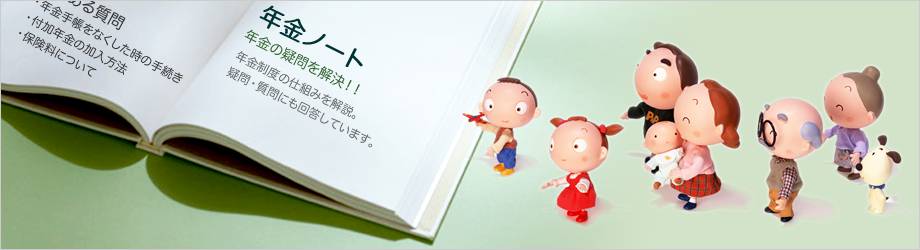パートの厚生年金加入条件・年収106万円の壁

厚生年金への加入条件が徐々に下げられており、多くのパートとフリーターが、厚生年金に加入しなければならない状態になっています。
加入条件を満たすと、社会保険料(年金保険料・医療保険料)を負担しなければなりません。
パートとフリーターの人は、あらかじめ厚生年金の加入条件を知っておきましょう。
厚生年金の加入条件緩和の経緯
昔、厚生年金は、会社員(サラリーマン・OL)が加入する年金制度として捉えられていました。
実際、厚生年金の加入条件が厳しかったので、フリーターやバイトで厚生年金に加入している人は珍しく、パートでも厚生年金に加入していない人は多かったです。
第3号被保険者に該当するパートは、収入を計算して、扶養を外れないように働いているので当然でしょう。
しかし、何度も法改正され、厚生年金への加入条件が緩和され続けています。
その結果、多くのパートとフリーターが、厚生年金に加入しなければならなくなりました。
厚生年金の加入条件
2016年10月に法改正され、次の条件全てを満たすと厚生年金に加入しなければならなくなりました。
- 勤務時間が週20時間以上
- 1ヶ月の賃金が8万8000円以上(年収106万円以上)
- 雇用期間が1年以上の見込み
- 従業員が501人未満の事業所で働いている
- 学生ではない
今後、「従業員が501人未満」の引き下げ・撤廃が検討されており、そうなれば、ほとんどのパートとフリーターが厚生年金に加入することになります。
つまり、第2号被保険者となるのです。
「106万円の壁」第3号被保険者のボーダーライン
第3号被保険者は、第2号被保険者の扶養に入ることで、年金保険料も健康保険料も納付する必要はありません。
しかし、パートとして働いて一定金額以上の収入を得ると、扶養を外れてしまうのです。
その金額が、年収106万円で、「106万円の壁」と呼ばれています。
ただし、106万円を超えただけでは扶養は外れず、「厚生年金の加入条件」を全て満たすと扶養を外れ、第2号被保険者として厚生年金保険料と健康保険料を納付しなければなりません。
年収が106万円をギリギリ超えたとすると、厚生年金保険料の労働者負担分が月約8000円、健康保険・介護保険料の労働者負担分が月約5000円なので、合計で月約1万3000円の社会保険料が発生します。
ちなみに、「厚生年金の加入条件」を満たさずに年収130万円を超えると、扶養を外れ、第1号被保険者として国民年金保険料と国民年金保険料を納付しなければならなくなり、月約2万5000~3万円の社会保険料が発生します。
この金額を見れば、第3号被保険者であるパートが、社会保険料を負担しなくてもいいように調整して働く意味が分かるでしょう。
パートが厚生年金に加入するメリット・デメリット
パートが厚生年金に加入するメリット・デメリットは、次のとおりです。
メリット
- 将来、老齢基礎年金に加え、老齢厚生年金も受給できる
- 条件を満たせば、障害厚生年金・遺族厚生年金が支給される
- 条件を満たせば、健康保険の傷病手当金・出産手当金・出産育児一時金などが支給される
- 会社が厚生年金保険料・健康保険料の半額を負担してくれる
デメリット
- 社会保険料(年金保険料・医療保険料)を納付しなければならない
こう見ると、パートでも厚生年金に加入した方が得のイメージが強くなりますが、実際、第3号被保険者であるパートは、将来の年金額受給額を増やすために働いているのではなく、目先の生活費を稼ぐために働いており、厚生年金加入を嬉しく思っている人は少ないでしょう。
扶養でいれば、国民年金保険料を納付しなくても納付したことになりますし、健康保険料も負担する必要がないので、当然です。
したがって、パートは、今後しばらくの間、「106万円の壁」を意識して働くことになると思います。
会社も、社会保険料の半額を負担したくないので、106万円を超えないように協力するはずです。
ただ、その状態が続けば、どうにか第3号被保険者であるパートを厚生年金に加入させようと考え、年収基準を下げるかもしれません。
このように、パートを厚生年金に加入させる攻防が続いていますが、その影響を一番受けているのがフリーター・バイトであり、稼ぎ頭となる配偶者がいないにもかかわらず、社会保険に加入しなければならなくなり、生活が苦しくなっています。
関連記事
公的年金制度の第1号被保険者は、20歳から60歳まで強制加入となり、国民年金保険料を自ら納付しなければなりませんが、自営業や無...
国民年金に加入義務のない者が、自分の意思で国民年金に加入することができる任意加入制度について説明いたします。 国民年金...