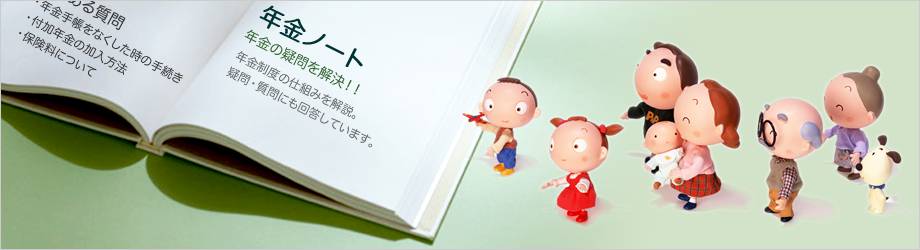合算対象期間とは?わかりやすく解説
2019年02月16日老齢給付

老齢基礎年金の受給資格を判断する材料のひとつに合算対象期間がありますが、理解が難しいのが難点です。
この合算対象期間について、わかりやすく解説します。
合算対象期間とは?
合算対象期間とは、別名「カラ期間」と呼ばれており、老齢基礎年金の受給資格期間10年以上には算入されますが、老齢基礎年金額には一切反映されない期間のことです。
例えば、学生は、平成3年3月まで国民年金への加入を任意とされていました。
したがって、それ以前に任意加入しなくて国民年金保険料を納めていない期間がある場合、その期間は保険料納付済期間に該当せず、また、保険料免除期間にも保険料滞納期間にも該当しないことになります。
当然、その人物に責任はないため、受給資格期間の計算には算入されますが、国民年金保険料を納めていないので、老齢基礎年金額の計算には加えないのです。
(例)保険料納付済期間が35年、合算対象期間が5年の場合
【受給資格期間】 35年 + 5年 = 40年
【老齢基礎年金額】 35年
【受給資格期間】 35年 + 5年 = 40年
【老齢基礎年金額】 35年
なお、合算対象期間は、新法と旧法で異なっており、具体的には以下のとおりです。
昭和61年4月1日から国民年金が基礎年金として導入され、全国民が国民年金の適用を受けることになったため、このように合算対象期間の内容も異なっています。
昭和61年4月1日以後(新法)の合算対象期間
昭和61年4月1日以後(新法)の合算対象期間は、次のとおりです。
- 国民年金の任意加入被保険者になることができる期間のうち被保険者とならなかった期間(第2号被保険者又は第3号被保険者及び60歳以上であった期間を除く)
- 第2号被保険者期間のうち20歳前及び60歳以後の期間
- 任意加入して保険料を納付しなかった海外在住期間
昭和61年4月1日前(旧法)の合算対象期間
昭和61年4月1日前(旧法)の合算対象期間の参考例として、一部を紹介します。
- 国民年金に任意加入できた期間のうち被保険者とならなかった期間(60歳前の期間に限る)
- 国民年金の任意脱退の承認に基づき被保険者とされなかった期間
- 国会議員であった期間(60歳前の期間に限る)のうち昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間
- 日本国籍を有し日本国内に住所を有しなかった期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)のうち、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間
- サラリーマンの妻で、任意加入したが保険料を納付できなかった期間
平成3年3月31日以前の合算対象期間
平成3年3月31日以前の合算対象期間は、次のとおりです。
- 20歳以上の学生で、任意加入したが保険料を納付しなかった期間
関連記事
2019年02月21日老齢給付
第1号被保険者が納付する国民年金保険料は、すべての人が同じ金額となっています。 一方、第2号被保険者が納付する厚生年金...
2019年02月12日老齢給付
本来、65歳から支給を受けることができる老齢基礎年金ですが、66歳以上から支給を受けることにより、受給額を増やすことができます。 ...